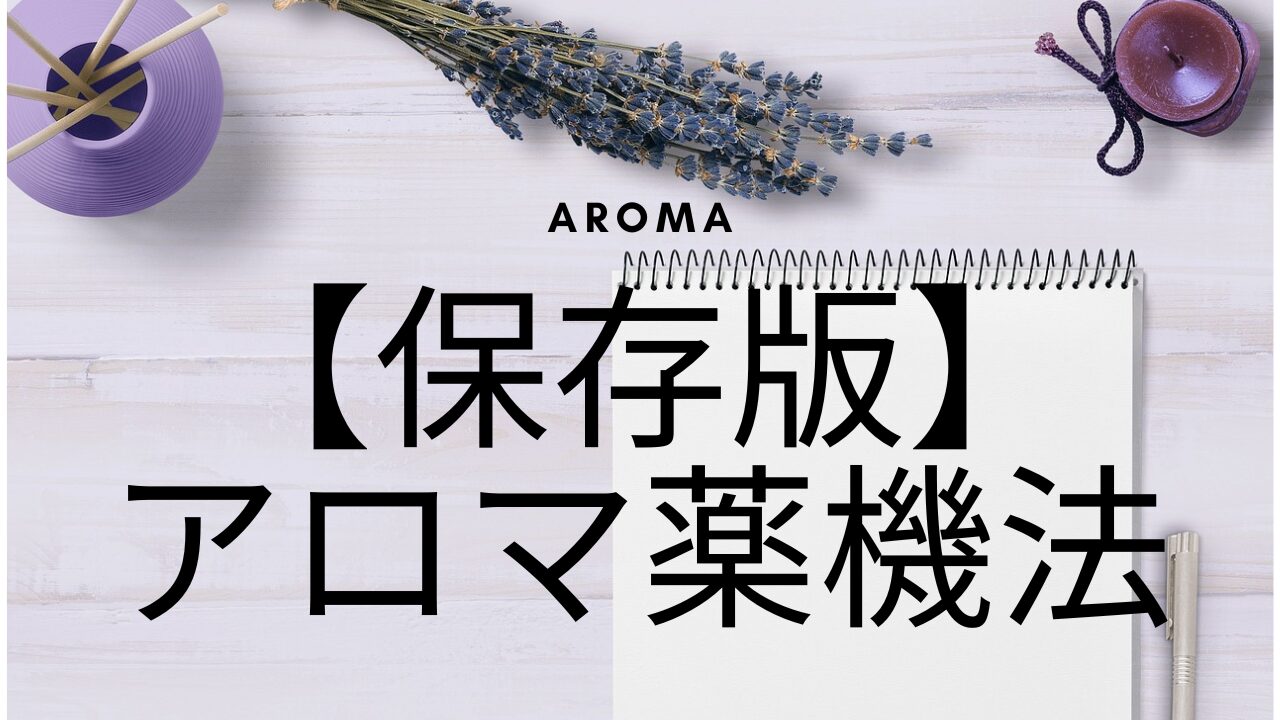アロマの薬機法:使い方や表現によっては規制対象
「自分の作ったアロマ製品を販売してみたい」「ナチュラルで安心な商品を届けたい」そんな思いで、手作りアロマの販売を目指す方が増えています。※本記事では混乱を避けるため、“アロマ”はすべて“精油を使用した商品”を指す言葉として使います。

アロマ製品を扱うときに注意したいのが、【薬機法(旧・薬事法)】です。これは、化粧品・医薬部外品・医薬品などの製造や販売方法について定めた法律で、違反すると罰則が科されることもあります。
アロマ製品も使い方や表現によっては薬機法の規制対象になります。たとえば、「肩こりに効く」「花粉症が治る」といった効果・効能をうたう表現は、医薬品扱いとなり、許可なしでは販売できません。
・アロマ製品の分類(雑貨/化粧品/医薬部外品など)
・手作りアロマを販売する際の注意点
・法的に安全な商品化のステップを、初心者にもわかりやすく解説します。
・アロマの資格について知りたい方はコチラのリンクへお進みください。

【アロマは雑貨】扱いだが医薬品に分類されているのもある
市販されている精油の多くは「雑貨」として販売されています。これは、人体への使用を目的としていないためです。
・ルームスプレー
・ディフューザー
・アロマキャンドル
これらは薬機法の許可不要で販売可能ですが、注意すべきポイントがあります。

「肩こりに効く」など、効能効果をうたうと薬機法違反になる可能性があります!
アロマの使用目的によって分類が変わる
アロマ(精油)製品は、使い方・目的・表示によって以下のように分類されます。
| 分類 | 例 | 必要な許可 |
|---|---|---|
| 雑貨 | 芳香剤、キャンドルなど | 不要 |
| 化粧品 | マッサージオイル、アロマ化粧水など | 製造業・製造販売業の許可 |
| 医薬部外品 | 制汗スプレー、殺菌目的の製品など | 厳しい表示管理と許可制 |
| 医薬品 | ハッカ油・ユーカリ油など | 医薬品製造業・製造販売業の許可 |
手作りアロマ製品も薬機法の対象になる
「趣味で作ってるだけだし……」→ 誰かにあげたり売った瞬間に、薬機法の対象になる可能性あります。
アロマ注意が必要なケース
- アロマクリームやリップを効能目的で友人にプレゼントする。
- フリマアプリで自作のアロマスプレーを販売する。
アロマ参考にしたいケース
- 自分用に作って使う。
- ワークショップ形式で参加者が自分用に作る。
【アロマを商品化】製造業と製造販売業を知っておくべき基本知識
「製造販売業」と「製造業」名前は似ていますが役割や責任、必要な許可が大きく異なります。
それぞれの違いをわかりやすく解説します。
【アロマを商品に】製造業とは?
「製品をつくることだけに特化した立場」です。

・医薬品や化粧品などを実際に製造する業務を行う。
・製造だけで、市場への出荷はできない。
・製品の品質や安全に関する最終責任は持たない。
・製造業として登録が必要です。
【アロマを販売】製造販売業とは?
製品を「市場に出す責任を持つ立場」です。

・製造または輸入した医薬品を販売・提供する。
・国内市場への出荷ができる。
・製品の品質管理や、安全管理(副作用・回収対応など)含めてすべての責任を負う。
・製造販売業として許可が必要。
| 許可 | できること | ポイント |
|---|---|---|
| 製造業許可 | 実際に製品を作る・包装・保管など | 作るだけで売れない! |
| 製造販売業許可 | 市場に出して販売する | 売るだけで作れない! |

| 区分 | 要件内容 |
|---|---|
| 申請者の資格要件 | 薬機法第5条第3号イ〜ヘに該当しないこと(過去の取消処分、禁錮刑、薬事法違反、薬物中毒などがない)。 |
| 総括製造販売責任者の資格 | 薬剤師、化学系学歴+実務経験、厚労省認定の知識・経験者などが対象。 |
| 品質保証責任者(GQP) | 品質管理を適切に行える能力があること。販売部門の影響を受けないこと。 |
| 安全管理責任者(GVP) | 安全確保業務を適切に遂行できる能力があること。販売部門から独立していること。 |
| 三者兼務の可否 | 同一所在地に勤務しており、業務に支障がなければ兼務可能。 |
【アロマを商品】にして販売するステップ
「自分のブレンドを商品にしてみたい」「アロマの香りで癒しを届けたい」そんな想いをカタチにするには、ちょっとした法律の知識と、正しいステップが必要です。このページでは、アロマを商品化して販売するための基本ステップを、わかりやすくご紹介します。
Step 1:自分で製造するか、OEMに委託する
- 自分で行う → 許可2種+設備が必要。
- OEMを使う → 委託先が許可を持っていれば販売可能。
Step 2:製品の目的・効能を明確にする
- 肌に使う?→化粧品類。
- 香りだけ?→雑貨
- 効能をうたう?→医薬部外品・医薬品の可能性。
製造販売業・製造業の許可申請・届出の手続き届出先は都道府県
製造販売業の申請手続きは、事業所や製造所が所在する都道府県の主管課で行います。具体的な手順や必要書類は都道府県ごとに異なる場合がありますので、詳細は各都道府県庁にお問い合わせください。以下に、いくつかの都道府県の関連情報を示します。
・北海道
・岩手
・群馬県
・沖縄県
・福岡県
アロマと薬機法を知れば、安心して届けられる
アロマ製品を、もっと多くの人に届けるために。法律という「壁」を正しく理解し、正規の方法で販売すれば、自信をもって「安心・安全」な商品を提供することができます。

まとめ
私が資格を取得した当時、「いつか自分だけのアロマ商品を作ってみたい」――そんな夢を抱いていました。でも、いざ調べてみると、思っていた以上に多くのルールやプロセスが必要で、
正直、驚きと戸惑いの連続でした。
それでも一つ一つを知っていくうちに、普段、私たちが何気なく手に取っている商品は、たくさんの人の努力と時間、そして想いによって生まれているんだと、深く実感するようになりました。
この記事が、かつての私のように「自分の想いをかたちにしたい」と願う方の小さなヒントや勇気になりますよう。そしてこの記事を読んでくれた方が、次の一歩を踏み出せますように。